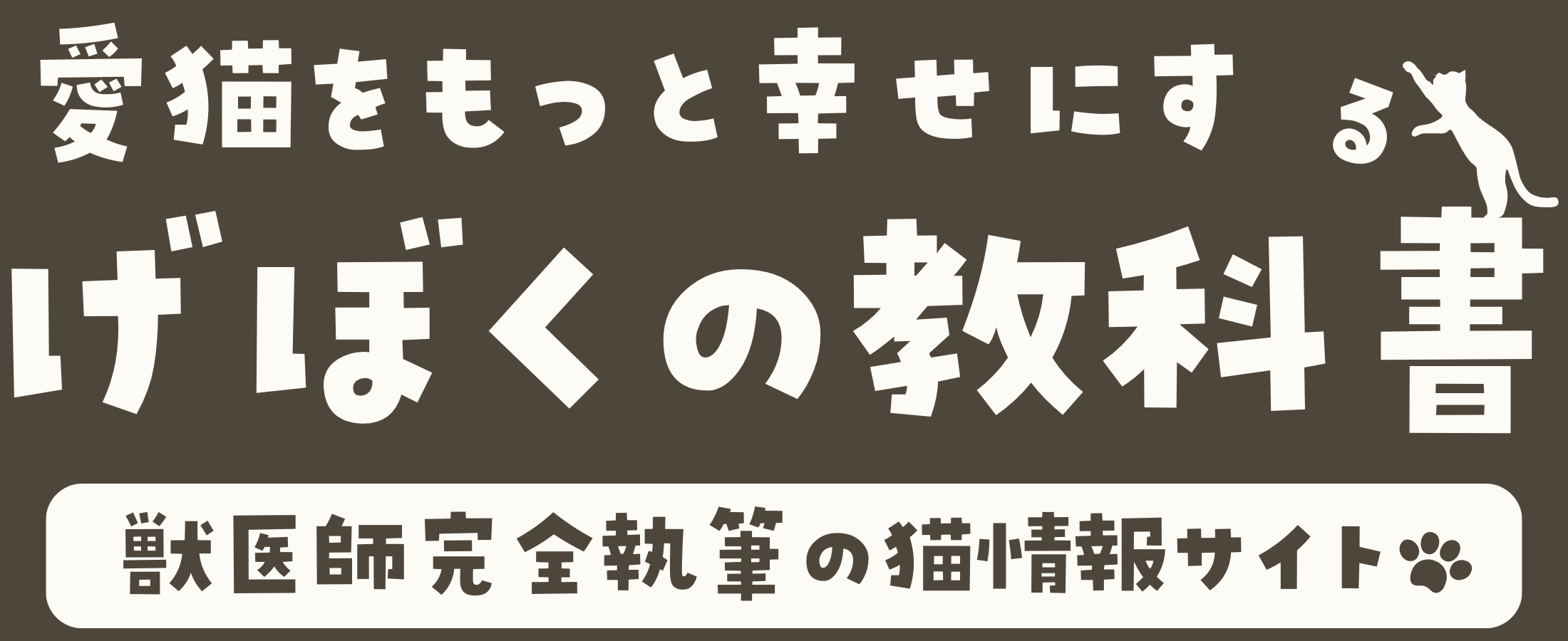愛猫が突然くしゃみや鼻水を連発し始めたら、心配になりますよね。多くの場合、その原因は私たち人間の風邪に似た「猫の上部気道感染症(いわゆる猫風邪)」です。特に子猫や、新しくお家に迎えたばかりの猫ちゃんによく見られます。
この記事では、猫の急なくしゃみや鼻水の原因として最も一般的なものから、まれだけれど注意が必要な病気まで、その見分け方、動物病院での治療、そしてご家庭でできるケアについて、獣医師が詳しく、そして分かりやすく解説します。
なぜ?くしゃみ・鼻水のメカニズム
猫のくしゃみや鼻水は、鼻の粘膜が何らかの刺激によって炎症を起こすことで発生します。この炎症のサインは、主に鼻腔や副鼻腔といった「上部気道」で起こっています。
猫の場合、急性の症状の約80%は、ウイルスや細菌による感染症が原因です。これらの病原体が鼻の粘膜に感染することで、粘膜が腫れたり、過剰な分泌物(鼻水)が出たり、そしてそれらを排出しようとする反射として「くしゃみ」が起こるのです。
考えられる原因と症状(発生頻度順)
急なくしゃみや鼻水には、様々な原因が考えられます。ここでは、遭遇する可能性が高い順に、それぞれの病気の特徴を解説します。
【非常に多い】ウイルス性鼻気管炎(猫風邪)
急性のくしゃみ・鼻水の原因として、圧倒的に多いのが「猫風邪」です。その病原体の二大巨頭が「猫ヘルペスウイルス」と「猫カリシウイルス」で、急な発症の8割以上がこのどちらか(または両方)の感染によると言われています。
1. 猫ヘルペスウイルス1型(FVR)
一度感染すると体内に潜伏し、ストレスなどで免疫が落ちた時に再発を繰り返すのが特徴です。
- 特徴的な症状:
- 突然の、激しいくしゃみの連発(発作性くしゃみ)
- 最初はサラサラ、次第にネバネバした膿のような鼻水や目やに(両側性)
- ひどい結膜炎(目が赤く腫れる、しょぼしょぼする)
- 発熱、元気・食欲の低下
- 子猫では重症化しやすく、呼吸困難に陥ることもあります。
2. 猫カリシウイルス(FCV)
ヘルペスウイルスと症状は似ていますが、最大の特徴は「口の中」に現れます。
- 特徴的な症状:
- 舌や上顎にできる痛みを伴う潰瘍(口内炎)
- 発熱、元気消失
- くしゃみや鼻水はヘルペスほど激しくないことが多い
- まれに、関節炎による痛みで歩き方がぎこちなくなることもあります。
【比較的多い】その他の原因
3. 異物
草の穂や植物の種、小さなゴミなどが鼻の中に偶然入ってしまうことがあります。
- 特徴的な症状:
- 突然の、非常に激しいくしゃみ
- しきりに顔をこすりつけたり、前足で鼻をかこうとしたりする
- 片方の鼻からだけ鼻水や鼻血が出ることが多い
- 鼻の奥(鼻咽頭)に詰まると、「ゲーゲー」と吐きそうな素振りを見せることもあります。
4. 細菌感染症
ウイルス感染に続いて二次的に細菌が増殖したり、他の猫から直接細菌がうつったりします。多頭飼育環境で問題になりやすいです。
- 主な原因菌と症状:
- ボルデテラ・ブロンキセプティカ: 人間の百日咳菌の仲間。くしゃみ、鼻水、発熱のほか、「ケンケン」という乾いた咳が出ることが特徴です。
- クラミジア・フェリス: 主にしつこい結膜炎がメインの症状。最初は片目から、次第に両目に広がります。くしゃみや鼻水は比較的軽度です。
- マイコプラズマ: こちらも結膜炎が主な症状。単独での発症より、ウイルス感染症に合併することが多いです。
【まれだが見逃せない】重篤な病気
急な症状で始まるものの、なかなか治らずに慢性化したり、悪化したりする場合は、以下のような病気も疑われます。
- クリプトコッカス症: カビ(真菌)の一種による感染症。慢性的な鼻水・鼻血や、鼻すじが盛り上がって変形する「ローマ鼻」が特徴的ですが、急に発症することもあります。
- 鼻腔内腫瘍: 高齢の猫に多いです。最初は片側性の鼻水・鼻血が続き、次第に悪化します。
- アレルギー性鼻炎: 猫では非常にまれです。特定の季節にだけ、サラサラした鼻水やくしゃみが出ます。
診断と治療
動物病院での診断
正確な診断のため、獣医師は飼い主さんからのお話と診察所見、そして必要に応じて検査を組み合わせて原因を探ります。
- 問診: いつから、どんな症状か、ワクチン接種歴、生活環境などを詳しくお聞きします。
- 身体検査: 全身の状態、目や鼻、口の中を詳しく観察します。
- 感染症の検査: 結膜や喉の奥を綿棒でこすり、どのウイルスや細菌がいるかを調べるPCR検査を行うことがあります。
- 画像検査: 異物や腫瘍が疑われる場合は、麻酔をかけてレントゲンやCT検査、鼻の内視鏡(鼻鏡)検査を行うことがあります。
治療法
治療は、原因と重症度によって異なります。
- ウイルス感染(猫風邪): ウイルス自体を直接退治する特効薬は限られているため、猫自身の免疫力でウイルスを克服できるようサポートする治療(対症療法)が中心となります。
- 抗生物質: 細菌による二次感染を防ぐために処方されます。
- 点眼薬・点鼻薬: 目やにや鼻水を和らげます。
- インターフェロン: ウイルスの増殖を抑え、免疫を助ける注射です。
- 重症の場合: 食欲がなく脱水している場合は、点滴や栄養補給のために入院が必要になることもあります。
- 細菌感染: 原因となっている細菌に有効な抗生物質を投与します。
- 異物: 麻酔をかけて、内視鏡や鉗子(かんし)を使って慎重に取り除きます。
病院に行くべき?迷ったらまず相談を
愛猫の様子が「いつもと違うな」と感じたら、それが受診を考える最初のサインです。また、新しく保護した猫がくしゃみや鼻水の症状を見せるのは非常によくあるケースですが、自己判断で様子を見るのは禁物です。まずはかかりつけの動物病院に電話で相談し、指示を仰ぐのが最も安全で確実な方法です。
その上で、愛猫の状態を正確に獣医師に伝えることが、的確な診断への近道になります。ここでは、特に注意して観察し、獣医師に伝えるべきポイントを「注意サイン」と「緊急サイン」に分けて解説します。
獣医師に伝えるべき「注意サイン」
以下のような症状が見られる場合は、計画的な受診が必要です。電話で相談する際に、これらの情報を具体的に伝えましょう。
- 症状の期間と経過: 「3日前からくしゃみが出て、昨日から黄色い鼻水に変わった」など、いつから、どんな症状が、どう変化したかを伝えます。一般的な猫風邪は10〜14日で改善傾向が見られますが、2週間以上続く、または悪化している場合は、別の病気の可能性も考えられます。
- 元気・食欲の状態: 「ごはんは食べるが、いつもより少ない」「一日中寝ていて、あまり動かない」など、普段との違いを伝えます。特に24時間以上何も食べない場合は、必ず伝えるべき重要な情報です。
- 鼻水や目やにの色・性質: 「サラサラの透明な鼻水」「緑色でネバネバした目やに」など、色や粘り気を具体的に伝えます。黄色や緑色の膿のような分泌物は、細菌感染のサインです。
- 症状の出方: 「片方の鼻からだけ鼻水が出ている」「鼻血が混じる」といった特徴は、異物や腫瘍などを疑う重要な手がかりになります。
- 目の状態: 目の表面が白く濁る、しょぼつきがひどいなど、目の異常も大切な情報です。
【緊急】直ちに病院へ!危険なサイン
以下の症状は、命に関わる可能性が高い緊急事態です。夜間や休日であっても、ためらわずに救急対応可能な動物病院へ連絡し、すぐに受診してください。
- 呼吸の異常
- 口を開けてハアハア呼吸する(開口呼吸): 重度の呼吸困難を示しています。
- 呼吸が苦しそう: 安静時でも呼吸が速い、お腹を大きく動かして呼吸している。
- 舌や歯茎の色が悪い(チアノーゼ): 青紫色になっている場合、極度の酸素不足で非常に危険です。
- 意識・反応の低下
- ぐったりして動かない: 呼びかけへの反応がほとんどない、起き上がれない。
- その他の重篤な兆候
- 明らかな脱水: 首の皮膚をつまんでも戻りが遅い、目が落ちくぼんでいる。
- 鼻の変形: 鼻すじが腫れて形が変わってきた(ローマ鼻)。
- 特に子猫や高齢猫、持病のある猫は、症状が軽く見えても急変することがあります。少しでも普段と違う様子があれば、早めに相談しましょう。
ご家庭でできる!愛猫のためのホームケア
猫風邪などの軽い症状の場合、ご家庭でのケアが回復を大きく後押しします。愛猫が少しでも快適に過ごせるよう、以下の点を試してみてください。
1. 食欲をサポートする
鼻が詰まると匂いがわからなくなり、食欲が落ちてしまいます。猫にとって食事は体力維持の源泉です。
- 香りの強いフード: ウェットフードや、魚の風味の強いフードを試してみましょう。
- 少し温める: 電子レンジで人肌程度に温めると、香りが立って食欲をそそります。
2. 鼻づまりを和らげる
- 湿度を上げる: 加湿器を使ったり、洗濯物を室内に干したりして、部屋の湿度を保ちましょう。
- 蒸気浴: 猫をお風呂場に連れて行き、シャワーで蒸気を立てた空間に10〜15分ほどいてもらうと、鼻の通りが楽になります。
3. こまめに綺麗にする
- 目やにや鼻水で汚れた顔を、湿らせたコットンやガーゼで優しく拭き取ってあげましょう。皮膚のただれを防ぎ、猫の不快感を和らげます。
4. 安静な環境を整える
- 静かで、暖かく、安心して休める寝床を用意してあげてください。十分な休息が回復には不可欠です。
予防のためにできること
- ワクチン接種: 猫ヘルペスウイルスと猫カリシウイルスは、混合ワクチンで感染を予防したり、感染しても症状を軽くしたりできます。ワクチンプログラムについては、獣医師とよく相談しましょう。
- ストレスの軽減: ストレスは免疫力を低下させ、特にヘルペスウイルスの再発の引き金になります。穏やかで安心できる生活環境を心がけましょう。
- 完全室内飼育: 外の猫との接触を避けることが、感染症予防の最も確実な方法です。
- 衛生的な環境: 食器やトイレを清潔に保ち、新しい猫を迎える際は、最初の1〜2週間は隔離して健康状態を確認しましょう。
急なくしゃみや鼻水は、多くは一過性の猫風邪ですが、中には深刻な病気が隠れている可能性もあります。症状が長引く、ぐったりしている、食欲がない、呼吸が苦しそうといった場合は、ためらわずに動物病院を受診してくださいね。