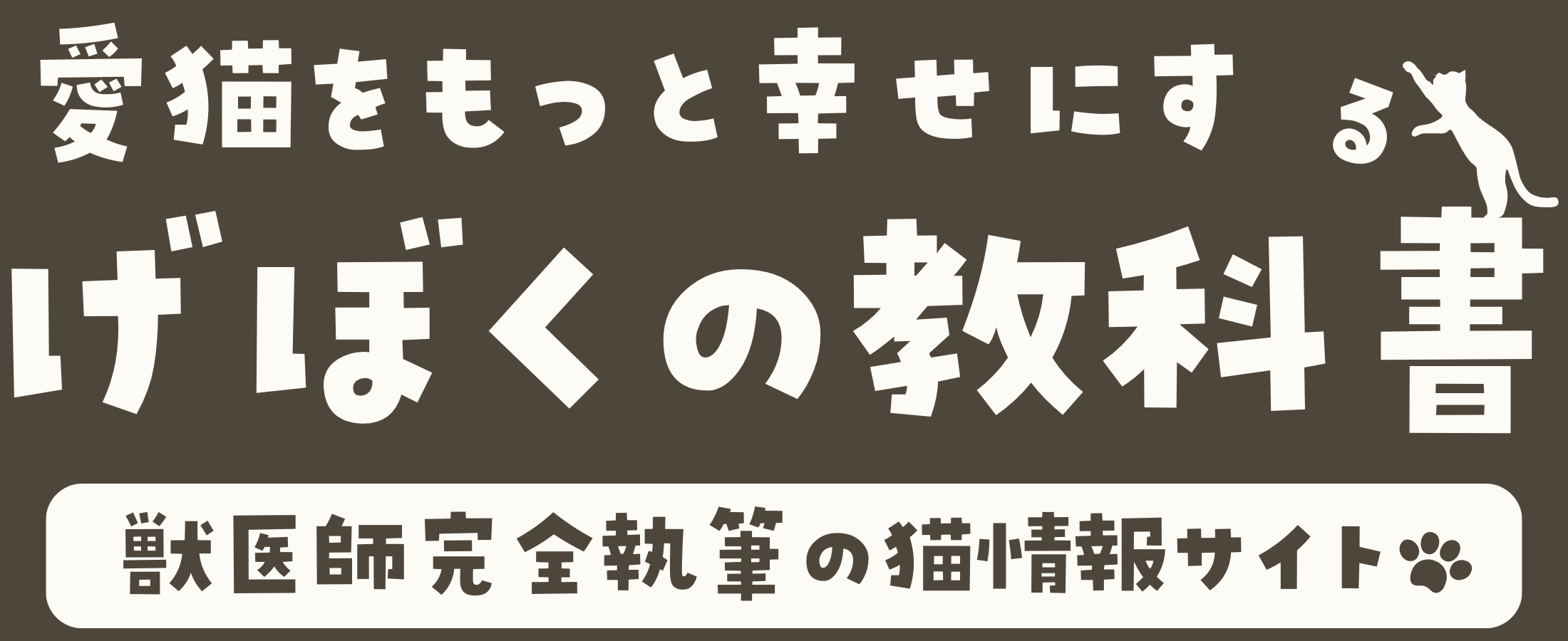猫の慢性腎臓病(CKD)とは
「最近、うちの子よくお水を飲むようになったな」「おしっこの量が増えたかも?」
そんなささいな変化が、実は「猫の慢性腎臓病(CKD)」のサインかもしれません。
猫の慢性腎臓病は、特にシニアの猫ちゃんにとって、とても身近な病気の一つです。数ヶ月から数年という長い時間をかけて、腎臓の働きがゆっくりと低下していきます。残念ながら、一度失われた腎臓の機能は元に戻ることはありません。
しかし、悲観しないでください。早い段階で病気に気づき、適切な治療とケアを始めることで、病気の進行を穏やかにし、愛猫が穏やかで快適な毎日を長く過ごせるようにサポートすることが可能です。
この記事では、獣医師の視点から、猫の慢性腎臓病について、その症状から最新の治療法、そしてご家庭でできるケアまで、飼い主さんが知りたい情報を分かりやすく、そしてやさしく解説していきます。愛猫との大切な時間を一日でも長く、幸せに過ごすために、一緒に学んでいきましょう。
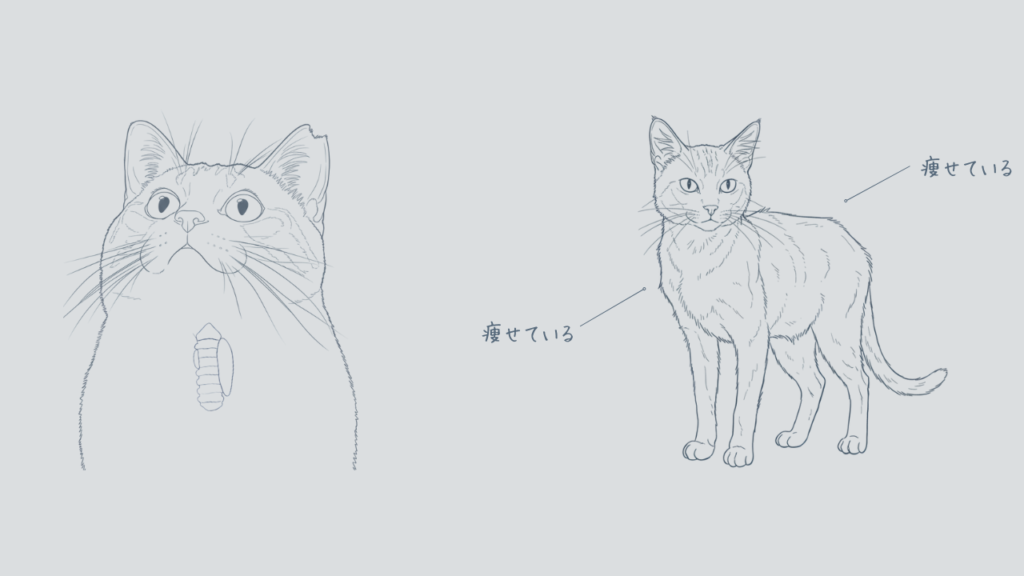
症状
猫の慢性腎臓病は、初期には症状がほとんどなく、飼い主さんが気づくのが難しい「静かな病気」です。多くの症状がはっきりと現れる頃には、腎機能がかなり低下していることが少なくありません。だからこそ、ささいな変化を見逃さないことが、早期発見の何よりの鍵となります。
飼い主さんが気づける「最初のサイン」
目に見える体調不良が現れるずっと前から、腎臓はSOSサインを出しています。特に重要なのが以下の2つの変化です。
お水を飲む量・おしっこの量がふえる(多飲多尿:たいんたにょう)
これは、最も重要で、多くの場合、唯一の初期症状です(1, 2, 3, 4, 5, 6)。
腎臓には、体に必要な水分を再吸収し、尿を濃縮する働きがあります。しかし、腎機能の約3分の2が失われると、この尿を濃縮する力が低下してしまいます(7, 8)。その結果、薄いおしっこが大量に作られる「多尿」が起こり、体は失われた水分を補おうとして、たくさんお水を飲む「多飲」になるのです。
<こんな変化に気づいたら>
- 水の器の減りが以前より早い
- お風呂場やシンクなど、いつもと違う場所で水を飲もうとする
- 猫トイレの砂の固まりが大きくなった、数が増えた
- おしっこの色が薄く、水のように無色に近くなった
- おしっこのツンとしたニオイが薄れた
最近、岩手大学の研究では、慢性腎臓病が進行すると、猫特有の尿臭の元となるアミノ酸「フェリニン」の排泄が減り、尿臭が弱まることも、飼い主さんが気づける新たなサインとして報告されています。
ゆっくりとした体重減少
見た目は元気で食欲もあるように見えても、気づかないうちに少しずつ体重が減っていることがあります。ある研究では、慢性腎臓病と診断された猫は、診断される前の半年から1年の間に、平均で約10%も体重が減少していたことが報告されています(9)。
月に一度、ご家庭で体重を測って記録する習慣は、この微妙な変化を捉えるためのとても有効な方法です。
病気が進行すると見られる症状
腎機能の低下がさらに進み、体の中に老廃物(尿毒素)が溜まってくると、より分かりやすい全身の症状が現れ始めます。これらの症状に気づいて動物病院を受診したときには、病気がかなり進行している(IRISステージ3〜4)ことも少なくありません(3, 8, 5)。
- 元気がない・ぐったりしている(元気消失): 最もよく見られる症状です。貧血や尿毒症によるだるさが原因です(1, 2)。
- 食欲がない(食欲不振): 尿毒素が脳に影響したり、吐き気を感じたり、口内炎の痛みなどから食欲がなくなります(1, 3)。
- 吐き気・嘔吐: 尿毒症による吐き気が主な原因です(1, 10, 11)。
- 脱水: おしっこで失われる水分に、飲む水の量が追いつかなくなると起こります。
- 口臭がする: 尿毒症特有のアンモニアのような口臭がすることがあります(1, 11, 12, 13)。
- 便秘: 慢性的な脱水で便が硬くなることが一因です(1)。
- 口の中のトラブル: 尿毒症による口内炎や潰瘍が見られることがあります(1)。
これらの症状は他の病気でも見られるため、正確な診断には動物病院での詳しい検査が必要です。
原因
「どうしてうちの子が腎臓病に?」多くの飼い主さんがそう思われることでしょう。猫の慢性腎臓病の根本的な原因は、残念ながら「特発性(とくはつせい)」、つまり特定できない場合がほとんどです。しかし、その背景には、猫という動物が生まれつき持っている体質や、様々なリスク要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
なぜ猫は腎臓病になりやすいの?
腎臓で起こっている「悪循環」
猫の慢性腎臓病の多くは、「慢性尿細管間質性腎炎(まんせいにょうさいかんかんしつせいじんえん)」という状態に陥っています(8, 14)。これは、腎臓の組織が長い間じわじわと炎症を起こし、次第に硬く変化(線維化:せんいか)してしまう状態です。
一度このプロセスが始まると、まるで悪循環に陥ります。
- 最初のダメージ: 何らかの原因で腎臓の機能ユニット(ネフロン)の一部が壊れます。
- 残されたユニットの過労: 健康な部分が、壊れた部分の仕事もカバーしようと無理をします。
- 過労によるさらなるダメージ: 無理がたたって、健康だった部分まで傷つき、炎症が悪化します。
- 炎症と線維化の進行: 炎症が続くと、腎臓の組織はどんどん硬い線維組織に置き換わり、働かなくなっていきます(1, 14)。
この悪循環には、血圧などを調節する「レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)」という体内システムが深く関わっており、治療薬(ACE阻害薬やARB)はこのシステムの暴走を抑えるために使われます(1, 14, 15)。
話題の「AIMタンパク質」
近年の東京大学・宮崎徹教授の研究によって、猫が特に腎臓病になりやすい根本的な理由が解明されつつあります。
多くの動物の血液中には「AIM」というタンパク質があり、腎臓に詰まった細胞の死骸などの“ゴミ”を掃除する役割を担っています。しかし、猫のAIMは生まれつきこの働きが弱く、腎臓に溜まったゴミをうまく掃除できないため、慢性的な炎症が起きて腎臓病になりやすいのではないか、と考えられているのです。この発見は、猫にとって慢性腎臓病がある意味で「宿命」ともいえる病気であることを示唆しています。
慢性腎臓病のリスクを高める要因
単一の原因ではなく、以下のような複数の要因が重なって発症のリスクを高めます。
- 年齢: 最も大きなリスク要因です。歳を重ねるごとに発症率は劇的に増加し、10歳以上の猫の30〜40%(10, 8, 16)、15歳以上では80%以上が罹患しているとの報告もあります(17)。
- 遺伝的な素因:
- 多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん): 腎臓に水のたまった袋(嚢胞)がたくさんできてしまう遺伝性疾患で、ペルシャやアメリカンショートヘア、スコティッシュフォールドなどに多く見られます(8, 18, 19)。
- その他、アビシニアン、シャム、ラグドールなども好発品種として知られています(8, 20)。
- 過去の病気やトラブル:
- 感染症: 細菌による腎盂腎炎(じんうじんえん)や、猫伝染性腹膜炎(FIP)など(14, 15, 21)。
- 中毒: ユリ科の植物や、車の不凍液(エチレングリコール)、特定の薬剤などを口にしてしまったことによる急性腎障害(8, 21, 22)。
- その他: 尿管結石、腎臓の腫瘍、心臓病など(1, 8, 21)。
- 関連・悪化させる要因:
- 歯周病: お口の中の慢性的な炎症や細菌が、腎臓病のリスクを高める可能性が指摘されています(9, 23)。
- 高血圧・甲状腺機能亢進症: これらの病気は慢性腎臓病と密接に関係し、原因にもなれば合併症にもなります(1)。
このように、生涯にわたる様々な小さなダメージが積み重なって、最終的に慢性腎臓病という状態に至ると考えられています。だからこそ、特定の原因を避けるだけでなく、日頃からの総合的な健康管理がとても大切になるのです。
診断方法
「うちの子、腎臓病かもしれない…」と動物病院を訪れたら、どのような検査をするのでしょうか。猫の慢性腎臓病の診断は、一つの検査だけで決まるものではありません。飼い主さんからのお話(病歴)、獣医師による診察、そしていくつかの検査結果を総合的に判断して行われます。
動物病院で行う主な検査
診断と、病気の進行度(ステージ)を判断するために、以下のような検査を体系的に行います。
血液検査
- 血清クレアチニン(Cre): 筋肉で作られる老廃物で、腎臓から排泄されます。昔からある腎機能の指標ですが、腎機能が75%ほど失われるまで正常値を示すことが多く、早期発見にはあまり向きません(8, 24)。また、筋肉量の少ない痩せた猫ちゃんでは、実際の腎機能よりも低い数値が出ることがあります(3)。
- 対称性ジメチルアルギニン(SDMA): クレアチニンよりも早く、腎機能が25〜40%低下した段階で数値が上昇し始める新しい検査項目です。早期発見に非常に役立つと期待されています(24, 25, 26, 27)。筋肉量の影響を受けにくいのも利点です(25, 27)。
- 血中尿素窒素(BUN): タンパク質の代謝物ですが、食事内容や脱水など腎臓以外の影響も受けやすいです。
- リン: 腎機能が落ちると血液中のリンの濃度が上がります。高すぎるリンはさらに腎臓を悪くするため、管理が重要です。
- その他: 体の酸性度(血液ガス)や電解質(特にカリウム)、貧血の有無(全血球計算)などを調べます(7, 28)。
尿検査
- 尿比重: 尿を濃縮する能力を調べる検査です。健康な猫で尿比重が低い場合(1.035未満)、腎機能低下を示す最も初期のサインの一つと考えられます(8, 24, 20)。
- 尿タンパク/クレアチニン比(UPC): 尿の中にタンパク質がどれくらい漏れ出ているかを調べます。タンパク尿は、腎臓にダメージがあるサインであり、病気を進行させる要因にもなります(15, 29)。
血圧測定
猫の慢性腎臓病では高血圧がよく見られ(約60%)、腎臓や目、脳などにさらなるダメージを与えるため、定期的な測定がとても大切です(1, 5, 24)。
画像診断
超音波(エコー)検査やレントゲン検査で、腎臓の大きさや形、内部の構造を観察し、腎結石や腫瘍、多発性嚢胞腎など、他の病気がないかを確認します(8, 28)。
IRISステージング:病気の進行度を知るものさし
診断と治療方針の決定には、国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)が定めたガイドラインが世界中で使われています。これは、血液検査(クレアチニン・SDMA)、尿検査(タンパク尿)、血圧の結果を元に、病気の進行度を4つのステージに分類するものです。
| IRISステージ | 血清クレアチニン (mg/dL) | 血清SDMA (μg/dL) | 飼い主さんから見た状態(目安) |
|---|---|---|---|
| ステージ1 | \<1.6 | \<18 | 非高窒素血症。 血液検査は正常でも、タンパク尿や腎臓の形の異常など、何らかの腎障害の証拠がある状態。症状はほぼない。 |
| ステージ2 | 1.6 – 2.8 | 18 – 25 | 軽度の腎性高窒素血症。 血液検査で軽度の異常が見られ始める。多飲多尿以外の症状はまだないか、非常に軽いことが多い。 |
| ステージ3 | 2.9 – 5.0 | 26 – 38 | 中等度の腎性高窒素血症。 食欲不振や嘔吐など、多くの全身的な症状が現れ始める。飼い主さんが「体調が悪そう」と気づくことが多い。 |
| ステージ4 | >5.0 | >38 | 重度の腎性高窒素血症。 ぐったりして重篤な尿毒症の症状を示し、命に関わる危険な状態。 |
※この分類は、猫ちゃんの状態が安定している時に行います。
飼い主さんから獣医師へ伝えるべき大切な情報
正確な診断のためには、日頃の猫ちゃんの様子を一番よく知っている飼い主さんからの情報が何よりも重要です。受診の際には、ぜひ以下の点を整理して伝えてください。
- いつから、どんな変化がありましたか?(例:「1ヶ月前からお水を飲む量が倍くらいになった」「今週に入ってから2回吐いた」など)
- 飲水量、尿量、食欲、体重の変化(具体的な量がわかればベストです)
- 今あげている食事やおやつの内容(商品名までわかると助かります)
- 過去の病気や、今飲んでいるお薬、サプリメントなど
治療・管理
猫の慢性腎臓病は、残念ながら完治させることはできません。そのため、治療の目標は「病気を治す」ことではなく、「病気の進行をできるだけ遅らせ、様々な症状を和らげ、愛猫の生活の質(QOL)を高く維持すること」にあります。
治療は、IRISステージや猫ちゃん一人ひとりの状態に合わせて計画され、生涯にわたって続きます。それはまるで、食事、水分、お薬をうまく組み合わせながらバランスをとっていくような、長い道のりです。
急に悪化した場合の治療(急性増悪)
普段は安定していても、脱水や感染症などをきっかけに、急にぐったりしてしまうことがあります。これを「急性増悪(きゅうせいぞうあく)」と呼び、命に関わる緊急事態です。この場合は、すぐに入院して集中的な治療が必要になります。
治療の中心となるのは点滴(静脈内輸液療法)です。点滴によって脱水を改善し、体内に溜まった毒素をおしっこと一緒に排泄させます。同時に、吐き気止めや食欲を出すお薬なども使い、猫ちゃんの苦痛を和らげます。
安定期の管理と進行を抑える治療
状態が安定している時期の管理は、以下の3つの柱を組み合わせて行います。
1. 食事療法:最も重要な治療法
慢性腎臓病の猫ちゃんにとって、生存期間を延ばし、QOLを改善することが科学的に証明されている最も重要な治療法が、腎臓病用の療法食です(30, 31, 32)。
- 療法食の特徴:
- リンとタンパク質の制限: 腎臓への負担を減らし、尿毒症の症状を和らげます。特にリンの制限は、病気の進行を遅らせる上で非常に重要です(32, 33)。
- 栄養素の調整: 不足しがちなカリウムやビタミンB群、腎臓を保護する効果が期待されるオメガ3脂肪酸などが強化されています。
- 高カロリー設計: 食欲が落ちても、少量でエネルギーを摂取できるように作られています。
IRISステージ2から療法食を検討し始め、ステージ3以降では強く推奨されます。ただし、急にフードを変えると食べてくれなくなることがあるため、今までのごはんに少しずつ混ぜながら、数週間かけてゆっくり切り替えてあげましょう。
2. 水分補給の維持:腎臓を守る基本
脱水は腎臓に大きな負担をかけます。常に新鮮なお水が飲める環境を整えることが非常に大切です。
- ウェットフードを中心に与える
- 水飲み場を家のあちこちに増やす
- 流水を好む子にはウォーターファウンテンを使う
病気が進行し、口から飲むだけでは水分が足りなくなった場合(ステージ3〜4)、ご家庭で皮下点滴を行うことがあります。これは飼い主さんが自宅で行うケアで、脱水を防ぎ、多くの猫ちゃんのQOLを劇的に改善させることができます。
3. 合併症に対するお薬での治療
慢性腎臓病は、腎臓だけでなく全身に影響を及ぼすため、様々な合併症に対してお薬が必要になります。
| 対象となる合併症 | お薬の種類 | 代表的な薬の名前 | 目的 |
|---|---|---|---|
| タンパク尿 | ARB / ACE阻害薬 | テルミサルタン (セミントラ®)、ベナゼプリル | 腎臓の血圧を下げ、タンパク質が尿に漏れ出るのを防ぎます。 |
| 高血圧 | カルシウムチャネル拮抗薬 | アムロジピン | 全身の血管を広げて血圧を下げます。 |
| 高リン血症 | リン吸着剤 | 水酸化アルミニウム、炭酸ランタンなど | 食事中のリンとくっついて、体内に吸収されるのを防ぎます。必ず食事と一緒に与えます。 |
| 貧血 | 造血刺激因子製剤 (ESA) | ダルベポエチンアルファなど | 赤血球を作るのを助け、貧血を改善します。 |
| 低カリウム血症 | カリウム補給剤 | グルコン酸カリウム | 不足したカリウムを補給します。 |
| 嘔吐・吐き気 | 制吐剤 | マロピタント (セレニア®) | 吐き気を抑え、食欲を改善しQOLを高めます。 |
| 食欲不振 | 食欲増進剤 | ミルタザピン (ミルタズ®)など | 食欲を刺激し、体重が減るのを防ぎます。 |
新しい治療薬と未来の治療法
- ラプロス®(ベラプロストナトリウム): 日本で承認されているお薬で、腎臓の血流を改善し、組織が硬くなる(線維化)のを抑えることで、腎機能の低下を抑制し、食欲などの症状を改善する効果が期待されます。主にIRISステージ2〜3で使われます。
- AIM創薬(AIM補充療法): 前述の宮崎徹教授の研究チームが進めている、画期的な治療法の開発です。機能していない「AIMタンパク質」を注射で補充し、腎臓のゴミ掃除機能を回復させることを目指しています。2025年に臨床試験が開始され、2027年頃の実用化が目標とされており、世界中の猫と飼い主さんから大きな期待が寄せられています。
- 再生医療: 幹細胞を使った治療も研究されており、その抗炎症作用などにより腎機能の低下を和らげる可能性が期待されています。
どんなに医学的に正しい治療計画でも、猫ちゃんがごはんを全く食べなかったり、お薬で強いストレスを感じたりするなら、それは成功とは言えません。獣医師と飼い主さんがチームとなり、愛猫の反応を丁寧に見ながら、その子にとってのベストな道を探していくことが、この長い病気との付き合いで最も大切なことなのです。
予防と家庭でできるケア
慢性腎臓病の多くは原因不明のため、完全に予防する方法はまだありません。しかし、腎臓への負担を減らし、発症のリスクをできるだけ低くするための「予防的なアプローチ」と、診断された後の愛猫の生活を支える「家庭でのケア」は、とても重要です。飼い主さんの日々の少しの心がけが、愛猫の腎臓を長く守ることにつながります。
腎臓を守るために今日からできる予防策
1. とにかく水分をたくさん摂ってもらう工夫
十分な水分は、おしっこの量を増やし、老廃物をスムーズに排泄させることで腎臓の負担を軽くします。
- 食事の主体をウェットフードにする。
- 新鮮なお水をいつでも飲めるように、水飲み場を複数設置する。
- 流れる水が好きな子にはウォーターファウンテンを導入する。
- ドライフードに少しお水を足してあげる。
2. 腎臓にやさしい食事管理
健康なうちから、腎臓に配慮した食事を心がけましょう。
- 年齢やライフステージに合った、質の良い総合栄養食を基本にする。
- 人間用の食べ物(特に加工品やチーズなど)は与えない。猫にとって塩分やリンが多すぎます。
- 話題の「AIM活性化フード」も、予防的な観点からは選択肢の一つになるかもしれませんが、効果があるかは不明です。特にすでに腎臓病と診断されている場合は、必ず獣医師に相談してください。
3. お口の健康を保つ(口腔ケア)
ひどい歯周病は、慢性腎臓病のリスクを高めることが分かっています(9, 23)。お口の中の細菌が全身に悪影響を及ぼすのを防ぐため、お家での歯磨きや、定期的な動物病院での歯科検診を心がけましょう。
4. 定期的な健康診断
最も効果的な「予防」は、病気の「早期発見」です。特に7歳を過ぎたシニア期に入ったら、元気に見えても年に1〜2回は健康診断を受けましょう。血圧測定、尿検査、血液検査(SDMAを含む)によって、症状が出る前の早いステージで病気を見つけ、早期に管理を始めることが可能です。
診断後の愛猫を支える家庭でのケア
慢性腎臓病と診断された後のケアは、治療と並行して行われる、飼い主さんによる日々のサポートが中心となります。愛猫のQOL(生活の質)を支えるための、大切な緩和ケアです。
食事のサポート
食欲不振は一番の悩みどころです。
- 療法食を少し温めて香りを立たせる。
- ウェットとドライを混ぜたり、いろいろなメーカーの療法食を試したりする。
- どうしても療法食を食べない時は、カロリーを摂ることが最優先です。獣医師と相談の上、猫ちゃんが喜んでくれる一般食などを与えることも考えましょう。
水分補給のサポート
脱水は腎臓病を悪化させます。前述の工夫に加え、病状が進んだ場合は、獣医師の指導のもとでご家庭での皮下点滴を行います。これは多くの猫ちゃんのQOLを劇的に改善する、とても重要なケアです。
トイレ環境の整備
足腰が弱くなった子のために、入り口が低いトイレを用意したり、周りにペットシーツを敷いたりといった配慮が必要です。自力でトイレに行けなくなったら、おむつの使用も検討します。
快適な生活環境づくり
腎臓病の猫は体温調節が苦手になりがちです。暖かく、静かで、安心して休める隠れ家を用意してあげましょう。ストレスは万病のもと。穏やかな環境を保つことが大切です。
投薬と心のケア
毎日の投薬は、猫ちゃんにも飼い主さんにも大きな負担です。投薬用のおやつなどを上手に使いましょう。そして何より、お薬の時間以外は、今まで通りたくさん撫でて、一緒に遊んで、穏やかな時間を大切にしてください。飼い主さんが笑顔でいることが、愛猫にとって一番の心の支えになります。
慢性腎臓病の管理は、時間も費用も、そして心労もかかる大変な道のりです。飼い主さん自身が心と体の健康を保つことが、結果的に愛猫への最善のケアにつながることを、どうか忘れないでくださいね。
よくある質問(FAQ)
猫の慢性腎臓病について、飼い主さんからよくいただくご質問にお答えします。
- Q1: 猫の腎臓病は治りますか?
- A: 残念ながら、現在の獣医療では一度壊れてしまった腎臓の機能を元に戻すことはできず、慢性腎臓病を完治させることはできません(8, 5)。しかし、治療の目標は病気の進行を穏やかにし、症状を和らげることで、猫ちゃんができるだけ長く快適な生活を送れるようにすることです。適切な管理によって、診断後も穏やかに長生きしてくれる猫ちゃんはたくさんいます(7, 24)。
- Q2: どんな症状が最初のサインですか?
- A: 最も一般的で、かつ最も早く現れるサインは、お水をたくさん飲み、おしっこをたくさんする「多飲多尿」です(2, 4, 12)。この時点では猫ちゃんは元気に見えることが多いため見過ごされがちです。また、気づきにくいですが、徐々に体重が減っていることも重要な初期サインの一つです(9)。しかし、初期症状といっても腎機能の約3分の2が失われるまで症状が現れないので、日頃から健康診断(特に尿検査)が大事です。
- Q3: 腎臓病用の療法食を食べてくれない場合、どうすればいいですか?
- A: 療法食の食いつきの悪さは、多くの飼い主さんが直面する悩みです。まずはウェットやドライ、様々なメーカーのものを試したり、フードを少し温めて香りを立たせたりする工夫をしてみてください。それでも食べない場合は、カロリーを摂取することが最優先です。かかりつけの獣医師に相談の上、一般食でも良いので猫ちゃんが喜んで食べてくれるものを与えることを検討してください。
- Q4: 治療費はどのくらいかかりますか?
- A: 治療費は猫ちゃんの状態や治療内容によって大きく異なりますが、生涯にわたる管理が必要なため、継続的な費用がかかります。あるペット保険会社の調査では、慢性腎臓病の猫の年間平均診療費が約27万円というデータも報告されています。定期的な検査、お薬、療法食、場合によっては皮下輸液などが主な費用となります。
- Q5: 腎臓病の猫におやつを与えてもいいですか?
- A: おやつを完全に禁止する必要はありませんが、その内容と量には細心の注意が必要です。特に、リン、塩分、タンパク質が多く含まれるジャーキーやチーズ、人間用の加工食品は腎臓に負担をかけるため避けるべきです(33)。腎臓病の猫ちゃんのために成分調整されたおやつも市販されていますので、与える際は必ずかかりつけの獣医師に相談しましょう。
- Q6: 話題のAIMの薬はいつ頃できますか?
- A: 宮崎徹教授の研究チームが進めているAIM創薬は、猫の腎臓病治療に大きな希望をもたらすものと期待されています。報道によると、2025年に猫用のAIM薬の臨床試験(治験)が開始され、早ければ2027年頃の実用化を目指しているとされています。まだ研究開発段階の新しい治療法であり、今後の進展が待たれます。
- Q7: 自宅で皮下点滴はできますか?
- A: はい、可能です。進行した慢性腎臓病による脱水を管理するため、多くの飼い主さんが獣医師の指導のもとでご自宅での皮下点滴を行っています。これは猫ちゃんのQOLを改善するための非常に重要な治療法の一つです。やり方や注意点については、動物病院で獣医師や動物看護師が丁寧に教えてくれますので、ご安心ください。
6. 参考文献
- Bartges, J. (2012). Chronic kidney disease in dogs and cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 42(4), 669-692. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2012.04.008
- Brown, C. A., Elliott, J., Schmiedt, C. W., & Brown, S. A. (2016). Chronic kidney disease in aged cats: clinical features, morphology, and proposed pathogeneses. Veterinary Pathology, 53(2), 309-326. https://doi.org/10.1177/0300985815622975
- Elliott, J., & Barber, P. J. (1998). Feline chronic renal failure: clinical findings in 80 cases diagnosed between 1992 and 1995. Journal of Small Animal Practice, 39(2), 78-85. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1998.tb03701.x
- Sparkes, A. H., Caney, S., Chalhoub, S., Elliott, J., Finch, N., Gajanayake, I.,… & Quimby, J. (2016). ISFM consensus guidelines on the diagnosis and management of feline chronic kidney disease. Journal of Feline Medicine and Surgery, 18(3), 219-239. https://doi.org/10.1177/1098612X16631234
- Polzin, D. J. (2013). Evidence-based step-wise approach to managing chronic kidney disease in dogs and cats. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 23(2), 205-215. https://doi.org/10.1111/vec.12032
- White, J. D., Norris, J. M., Baral, R. M., Malik, R., & Govendir, M. (2014). Naturally-occurring chronic kidney disease in Australian cats: a prospective study. Australian Veterinary Journal, 92(1-2), 18-25. https://doi.org/10.1111/avj.12138
- Polzin, D. J. (2011). Chronic kidney disease in small animals. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 41(1), 15-30. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2010.09.004
- Vaden, S. L., Giger, U., & Grauer, G. F. (2017). Canine and Feline Nephrology and Urology. Elsevier.
- Finch, N. C., Syme, H. M., & Elliott, J. (2016). Risk factors for development of chronic kidney disease in cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 30(2), 602-610. https://doi.org/10.1111/jvim.13917
- Marino, C. L., Lascelles, B. D. X., Vaden, S. L., Gruen, M. E., & Marks, S. L. (2014). Prevalence and classification of chronic kidney disease in cats randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint disease studies. Journal of Feline Medicine and Surgery, 16(6), 465-472. https://doi.org/10.1177/1098612X13511446
- Quimby, J. M., & Lappin, M. R. (2016). Feline CKD: Current therapies – what is achievable?. Journal of Feline Medicine and Surgery, 18(9), 693-705. https://doi.org/10.1177/1098612X16662494
- Polzin, D. J. (2013). Evidence-based step-wise approach to managing chronic kidney disease in dogs and cats. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 23(2), 205-215. https://doi.org/10.1111/vec.12032
- Bartges, J. (2012). Chronic kidney disease in dogs and cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 42(4), 669-692.
- Brown, C. A., Elliott, J., Schmiedt, C. W., & Brown, S. A. (2016). Chronic kidney disease in aged cats: clinical features, morphology, and proposed pathogeneses. Veterinary Pathology, 53(2), 309-326.
- Quimby, J. M., & Lappin, M. R. (2016). Feline CKD: Current therapies – what is achievable?. Journal of Feline Medicine and Surgery, 18(9), 693–705.
- Sparkes, A. H., Caney, S., Chalhoub, S., Elliott, J., Finch, N., Gajanayake, I.,… & Quimby, J. (2016). ISFM consensus guidelines on the diagnosis and management of feline chronic kidney disease. Journal of Feline Medicine and Surgery, 18(3), 219–239.
- Marino, C. L., Lascelles, B. D. X., Vaden, S. L., Gruen, M. E., & Marks, S. L. (2014). Prevalence and classification of chronic kidney disease in cats randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint disease studies. Journal of Feline Medicine and Surgery, 16(6), 465–472.
- Vaden, S. L., Giger, U., & Grauer, G. F. (2017). Canine and Feline Nephrology and Urology. Elsevier.
- Piyarungsri, K., & Pusoonthornthum, R. (2021). Prevalence of antibodies that bind to kidney tissues in unvaccinated and FVRCP-vaccinated cats. BMC Veterinary Research, 17(1), 199. https://doi.org/10.1186/s12917-021-02905-2
- Bartges, J. (2012). Chronic kidney disease in dogs and cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 42(4), 669–692.
- Vaden, S. L., Giger, U., & Grauer, G. F. (2017). Canine and Feline Nephrology and Urology. Elsevier.
- Polzin, D. J. (2011). Chronic kidney disease in small animals. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 41(1), 15–30.
- Finch, N. C., Syme, H. M., & Elliott, J. (2016). Risk factors for development of chronic kidney disease in cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 30(2), 602–610.
- Relford, R., Robertson, J., & Clements, C. (2016). Symmetric dimethylarginine: improving the diagnosis and staging of chronic kidney disease in dogs and cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 46(6), 941-960. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2016.06.005
- Hall, J. A., Yerramilli, M., Obare, E., Yerramilli, M., & Jewell, D. E. (2014). Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. Journal of Veterinary Internal Medicine, 28(6), 1676-1683. https://doi.org/10.1111/jvim.12453
- Braff, J., Obare, E., Yerramilli, M., Elliott, J., & Yerramilli, M. (2014). Relationship between serum symmetric dimethylarginine concentration and glomerular filtration rate in cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 28(6), 1699-1701. https://doi.org/10.1111/jvim.12461
- Brans, M., Daminet, S., Mortier, F., Duchateau, L., Lefebvre, H. P., & Paepe, D. (2021). Plasma symmetric dimethylarginine and creatinine in cats with and without chronic kidney disease: a comparative study. Journal of Veterinary Internal Medicine, 35(2), 941-950. https://doi.org/10.1111/jvim.16075
- Quimby, J. M., Smith, D., & Lunn, K. F. (2011). Evaluation of the effects of the angiotensin-converting enzyme inhibitor benazepril in cats with induced chronic renal insufficiency. American Journal of Veterinary Research, 72(3), 337-344.
- Brown, C. A., Elliott, J., Schmiedt, C. W., & Brown, S. A. (2016). Chronic kidney disease in aged cats: clinical features, morphology, and proposed pathogeneses. Veterinary Pathology, 53(2), 309–326.
- Ross, S. J., Osborne, C. A., Kirk, C. A., Lowry, S. R., Koehler, L. A., & Polzin, D. J. (2006). Clinical evaluation of dietary modification for treatment of spontaneous chronic kidney disease in cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, 229(6), 949-957. https://doi.org/10.2460/javma.229.6.949
- Elliott, J., Rawlings, J. M., Markwell, P. J., & Barber, P. J. (2000). Survival of cats with naturally occurring chronic renal failure: effect of dietary management. Journal of Small Animal Practice, 41(6), 235-242. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2000.tb03932.x
- Quimby, J. M., & Lappin, M. R. (2016). Feline CKD: Current therapies – what is achievable?. Journal of Feline Medicine and Surgery, 18(9), 693-705.
- Polzin, D. J. (2011). Chronic kidney disease in small animals. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 41(1), 15-30.